今年も建設・不動産関連の「資格」受験の季節が到来
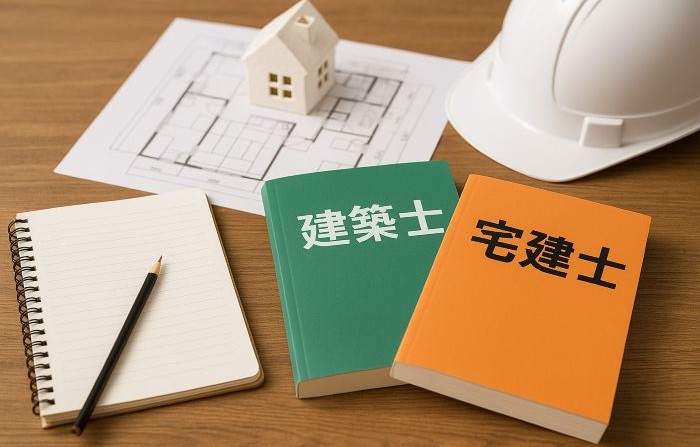
不動産の仲介や住宅の建築を業務として行う上で、求められる資格が複数あります。
代表的なものは「宅地建物取引主任者(以下、「宅建」)」や「建築士」です。
今回はこれらについて取り上げていきます。
不動産営業に必須の「宅建士」
宅建は、毎年約20万人が受験する人気資格で、不動産業者にとって必須の資格です。
試験があるのは例年10月の第3日曜日。
新卒採用をしている不動産関連企業の多くは、
内定者に対して資格取得を促しているはずです。
中には試験に向けて講座や模擬試験を企画して、
内定者一丸となって宅建合格を目指す企業もあります。
学生のうちに資格を取っておきたい最大の理由は「時間のゆとり」です。
合格の必要条件の一つは、まとまった学習時間です。
社会人よりも学生の方が時間にゆとりがあるのは言うまでもなく、
このタイミングでの資格取得がベストと言えます。
この他、試験勉強の習慣がある学生のうちに取り組むべきという理由もあります。
宅建に限らず、勉強そのものは社会人になってからも続けられますが、
合格・不合格を伴う試験のための勉強をするという機会はかなり少なくなります。
それまで身に付けてきた試験に向けた勉強方法や
取り組み方はいつの間にか失われてしまうもので、
試験勉強の習慣のある学生のうちに資格を取っておきたいところです。
社会人になってからということでは、不動産関連企業の人であれば宅建試験において
「5問免除」の制度を活用できるという強みがあります。
この制度を利用するには、国土交通大臣が指定する講習を受講して
「登録講習修了者証明書」の交付を受けることが必要です。
その上で、宅建試験を受験すると、本試験50問における、
46~50問目を解く必要がないだけでなく、自動的に5点が加算されます。
さらにいうと、一般の受験者が5問分に割いている勉強時間を、
他分野の勉強に費やすことができます。
社会人ともなると、隙間時間をいかに勉強に活用できるかが合格のカギとなり、
5問免除の制度も活用して早期の合格を目指しましょう。
「建築士」学科試験は7月開催
宅建と異なり、学生のうちに受験できないのが建築士です。
受験要件の一つは大学の建築系学科などを卒業することで、
多くは社会人になってからの挑戦となります。
ただ、大学を卒業すれば受験できるため、受験者の中には大学院生も一定数います。
このほか、かつては一級建築士については
2年以上の実務経験がなければ受験できませんでしたが、
2020年にこの要件が変更となり、現在は実務経験も不要となっています。
建築士試験の特徴は、ペーパーテストタイプの「学科試験」と、
学科試験で総合格基準点を上回った受験者が受けられる
「設計製図試験」の2つに分かれていることです。
一級建築士の場合、合格率は学科試験が例年15~20%、製図試験が30%ほどです。
比較的容易なのは、学科試験です。合計5つの科目があり、
覚えるべき量はかなり多くありますが、
テキストや問題集を使って勉強していくという
スタイルそのものは学生時代とほとんど変わりません。
合格率は製図試験よりも低いですが、比較的取り組みやすいはずです。
難関は「設計製図試験」。
学科試験をパスした受験者のみが受けることができます。
平行定規など製図のための専用ツールを活用して、
与えられた課題に対して設計図を製作していくという試験です。
試験時間は一級建築士の場合、6時間30分ですが、
事前準備が足りていないと描き切ることすら難しいです。
また、建築基準法など各種法令を遵守できなければ、
どれだけ図面を造り込んだとしても不合格になる可能性が高いです。
課題文を正確に読み解き、
各種居室などの条件をもれなく図面に反映させることが求められます。
一級建築士試験の学科試験と設計製図試験を同時に
パスするストレート合格の割合は数パーセントと、かなりハードルが高いです。
学科試験をパスできれば、製図試験に3度挑戦できるという免除制度もありますが、
ずるずると次年度、次々年度と繰り越すのは受験者自身の負担もかなり大きいです。
今年も7月に学科試験、10月に設計製図試験が実施されますが、
受験される方は、「この試験勉強は人生で今年が最後」という意気込みで、
万全な準備をしていきましょう。
(情報提供:住宅産業研究)





