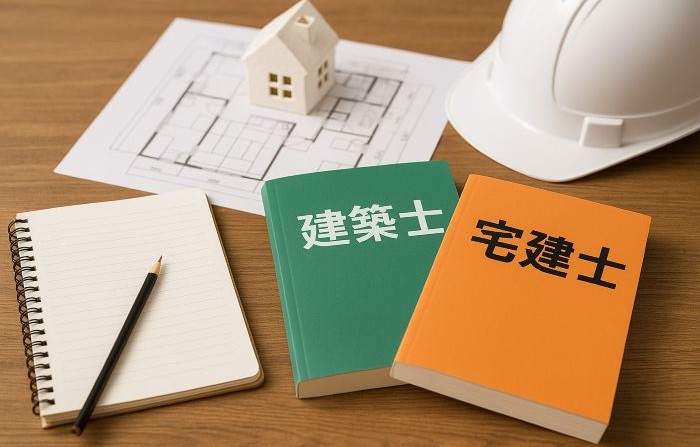みんなに優しい社会をつくるために住宅会社は何をする?

多様性が広がる今こそ求められるキッズデザイン
近年はライフスタイルの多様化が進んでおり、
DINKsや単身世帯、高齢者世帯などが増加してきています。
また、ライフスタイルの多様化は子どもを取り巻く環境にも及んでいます。
核家族化に加え、単独で外出する機会の多い都市部の子どもや、
共働き世帯の増加など、家庭ごとの事情はさまざまです。
こういった状況に対し、インクルーシブなキッズデザインの重要性は高まっていると言えます。
「子どもに優しいはみんなに優しい」ということで、
キッズデザインを取り入れた住宅は、その汎用性と価値が高まることが期待できます。
キッズデザインを住宅に取り入れるため、簡単な例をいくつか紹介しましょう。
例えば、視線と動線の設計があります。
LDKの見通しを確保しつつ、勉強コーナーや遊び場を配置すれば、
親が家事を行いながら子どもを見守れる設計になります。
こういった工夫は高齢者の見守りにも役立つでしょう。
ほかにも、段差や扉への配慮なども挙げられます。
角の丸め加工や引き戸、低めの収納など、物理的なバリアを減らすことで、
子どもに限らず、事故リスクを下げることができます。
こういったキッズデザインを効果的に訴求するには、
具体的にどのように提案すればよいでしょうか?
1つの方法としては、営業資料や見積書に、
「キッズデザインチェック項目」のようなものを明示することです。
「角丸処理:標準」、「引き戸採用:○箇所」、「学習コーナー:W×D 指定」
などといったように数字や製品名を入れると、
どこでどれくらいキッズデザインを取り入れているのか
ということがお施主様に伝わりやすくなります。
それらの項目に対して
「この箇所はお子様がケガなどをしないようにこういった工夫を取り入れています」
としっかりと説明をすることも忘れないようにしましょう。
キッズデザインは地域での信頼や
長期的な満足度につながる可能性もある投資だと考えると良いでしょう。
子育て世帯や高齢者世帯が安心安全な暮らしを送ることができれば、
紹介等にもつながってくるかもしれません。
キッズデザイン賞2025・住宅関連の主な受賞作
ここからは2025年のキッズデザイン賞における住宅関連の受賞作を見ていき、
家づくりで活かせるポイントを考えてみます。
受賞作の1つが、YKK APの「伸縮ゲート レイオス」です。
同製品は、敷地と道路の境界の広い間口を仕切る伸縮ゲートとして、
子どもの飛び出し防止や不審者の侵入抑制に効果を発揮します。
操作時の怪我を防ぐため、部品や形状など細部にこだわり設計されているのもポイントです。
YKK APのほかにも、三協アルミやノーリツ、コロナなど
各社が設備・建材で受賞をしています。
こういった設備・建材であれば、採用するだけで
簡単にキッズデザインを取り入れることができます。
一条工務店は、「モバイルーム」と「あかちゃんごはん」の2つで受賞しています。
モバイルームは仮設・移動可能な居住空間で、
優れた断熱性能や熱交換方式の換気システムを備え、
屋外の花粉や粉塵、温度などによる影響を抑制することで、
子どもや家族が安心して暮らせる快適な住環境を実現しています。
従来の仮設住宅は、子どもが育つ場所として、
十分な居住環境とは言えず、健康被害が生じる恐れがありましたが、
モバイルームはこうした課題を改善し、長期化する避難生活においても
健康被害のリスクを低減できる点が高く評価されました。
日常だけでなく有事の時も考えたキッズデザインというのは、大切な視点かもしれません。
あかちゃんごはんは、離乳食の時期の乳幼児を対象に、
月齢に合わせた離乳食の進め方や
献立レシピ、栄養バランス、食材リストやお役立ち情報などを、
LINEで毎週配信する無料コンテンツです。
このように、住宅そのものだけでなく、
付帯サービスでもキッズデザインというのは取り入れることができます。
ほかにも、AQ Groupは木育授業や廃材アートコンテスト、
カンナ削り体験といった木に触れるプログラムを通して、
子どもたちに地球環境貢献の大切さなどを
考える場を提供する「つくろう!木育フェス」で受賞。
クレバリーホームは住宅展示場や宿泊体験施設を活用し、
直下型地震に備える耐震構造の体験や、
親子で学ぶ防犯セミナー、家庭菜園を通じた食育プログラムなど、
多様な学びの機会を提供する「防災・耐候・防犯・食育 スクーリング」で受賞しており、
学びの場を提供することでの受賞が見られます。
こういった学びの場の創出も、キッズデザインの大切な要素となってきています。
いかがでしょうか?こういった受賞例を見ると、
意外と簡単にキッズデザインを自社に取り入れられる気がしませんか?
時代に即した付加価値向上の一手として、キッズデザインを選ぶのも良いかもしれません。
(情報提供:住宅産業研究)